「ホームセンター大手のカインズはパートやアルバイト従業員が65歳の定年を過ぎても働ける制度を本格導入する。」H30.9.8土 日経10面 企業・アジアBiz
記事にはさりげなく書いてありますが、カインズはもともと定年が60歳ではなく65歳だったと言っています。それをさらに延長するということです。
同じ記事には大手スーパーの定年等の扱いについて、一覧表になっていました。
ポイントを列挙してみると、このようになります。。
「再雇用の年齢上限を70歳から75歳に引き上げ」ライフコーポレーション
「定年を60歳から65歳に延長。再雇用後の上限も70歳から75歳に」サミット
「定年を60歳から65歳とし、再雇用後68歳まで就業可能に」いなげや
「65歳で定年後の再雇用の上限を70歳に。希望すれば75歳まで就業も」ヤオコー
これらは大手のスーパーの例ですが、定年60歳説にはもはや縛られてはいないということがわかります。
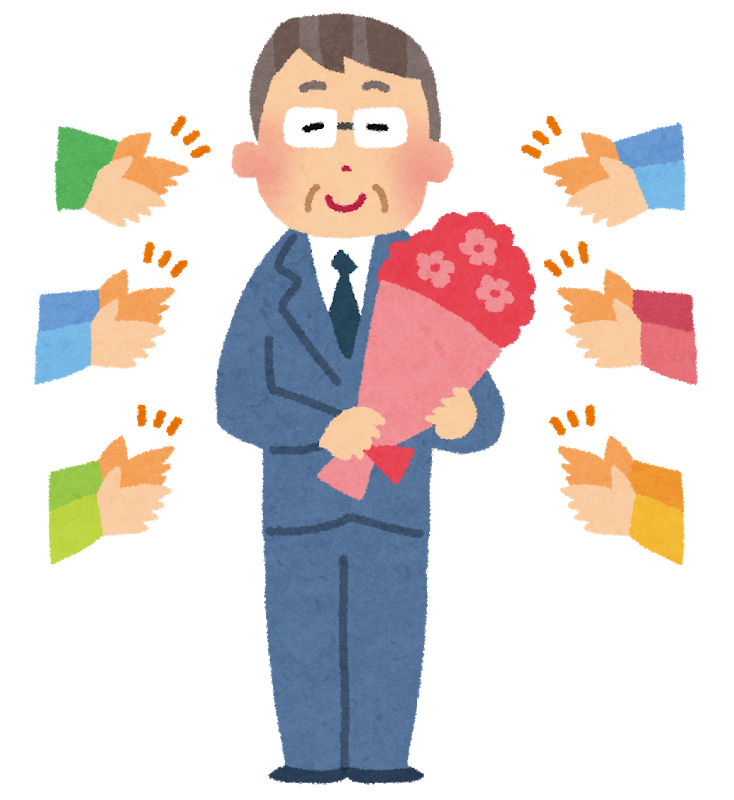
この定年60歳説はそもそもだれがいつ決めたものなのでしょうか。
私が社会人一年目だった頃はまだ昭和の時代で、その頃には確か55歳が定年の年齢だったと思います。
個人的なことで恐縮ですが、私はいま54歳ですので、就業規則の定めにもよりますが昭和の時代に生まれ、昭和の時代に55歳を迎えるサラリーマンだとすると、次の誕生日を迎えるともはや定年退職をするという仕組みだったということです。
作家の城山三郎著の「部長の大晩年」という小説はこのように始まります。
“永田耕衣、本名軍二は、満五十五歳で定年の日を迎えた。
勤続三十八年。退職時のポストは、製造部長兼研究部長。
勤務先は、三菱製紙高砂工場。戦前、関西での三菱グループを代表する大工場であり、従業員千八百人。その工場長は、三菱系企業の関西での会合などでは、いつも幹事役をつとめる立場に在った。
それほどの大工場で、耕衣は、工場長、工場次長に次ぐナンバー・スリーのポストについていたのである。”
部長なのにナンバー・スリーというところが、サラリーマン社会の悲哀をにじませる出だしになっていますが、とにかくこの小説の主人公は55歳で定年になっています。
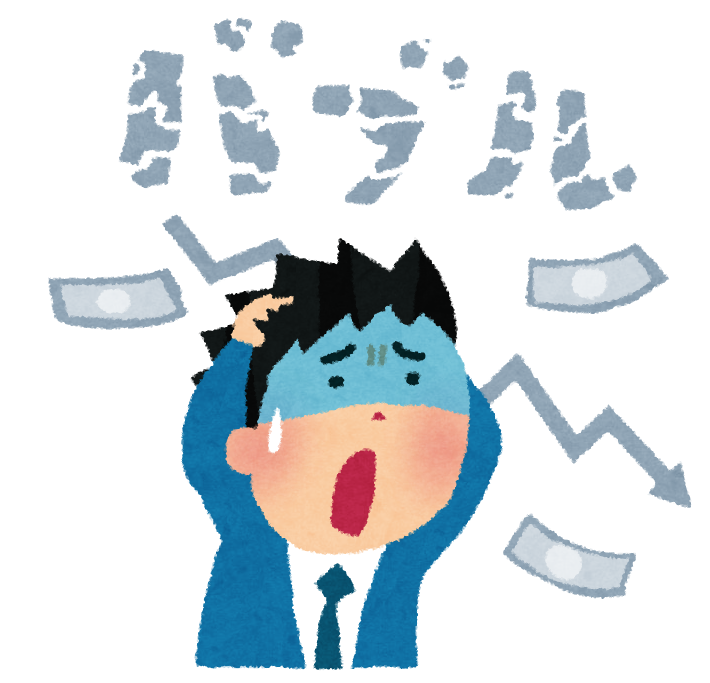
実は定年が60歳になったのは1994年(平成6年)のことです。
バブル崩壊が1991年から1993年ですから、失われた20年と言われる低成長期が始まるその年だったということです。
この年に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正されて60歳未満定年制が禁止になっています。このタイミングですべての企業が55歳定年から60歳定年以上にスイッチしたはずです。
むろんこの法律は1994年に突然施行されたわけではなく1986年(昭和61年)に60歳定年が企業への努力義務になり、企業は制度変更を順次行い、60歳定年に移り変わっていったのだと思います。
わたしが社会人になったのは1987年(昭和62年)でしたので、まだ55歳定年の会社が存在する時代でした。
そしていまや平成が終わろうとする時代には60歳定年さえ有名無実化しようとしているということです。
再びホームセンター大手のカインズさんについての記事です。
「9月末までにパート社員らの契約を全て有期から無期雇用に転換し、定年も60歳から65歳までに延長する。さらに65歳以降についても1年ごとの更新で長く働けるようにする。パートの時給は現状のままの水準を維持する。」同記事
時給は維持されるわけですから、採用コスト分会社の負担が軽減されることになります。
正社員と契約、有期、パートの垣根が低くなり、定年60歳という定めがまるで最低賃金のような扱いに変化していくとするならば、今一度、正社員とはなんだろう?なぜ契約社員か?いつまで有期なのか?適正な定年年齢はなにか?ということを、会社の成長を基本とする全体最適の考え方に基づいて、再構築する必要があります。
社長の手腕が問われるということです。

ガッツだぜ!社長‼