「現状の労基法でも給与の一部であれば労使協定を結んで、現金以外で支払えるという「例外」がある。」H30.8.3金 日経7面(金融経済)
この記事は少し違っていると思います。
「労使協定を結んで」覆すことができるのは「賃金支払い5原則」のうち「③全額払い」の原則のことです。

社会保険労務ハンドブック 平成29年度版 P83 全額払い には、次のように記されています。
「賃金は、その全額を支払わなければならない(労基24①本文)。ただし、次のいずれかの場合には、賃金の一部を控除して支払うことができる(労基24①但し書)」
「現金以外で支払える」(同記事)と「控除して支払う」(同ハンドブック)は同じではありません。
「控除して支払う」(同ハンドブック)とは「給与所得税の源泉徴収、地方税の特別徴収(所税183地方税321の5)、各種社会保険法による保険料の控除(徴収31、厚保84、健保167)」や「労働組合費の天引(チェック・オフ)、工場売店の売掛代金の控除、委託管理による貯蓄金の控除などが、これにあたる」としています。
つまり「現金以外で支払える」(同記事)というのは、あくまでも本人に支払うという意味であるのに対して「控除して支払う」(同ハンドブック)は控除されたものは本人以外のところへ支払われるということを意味しています。貯蓄金であっても委託管理者のもとへ行くので、本人の自由になるマネーではないという点で「控除」にあたります。
「GMOインターネットグループは今春、ビットコインで給与の一部を支払えるようにした。」同記事

これは「③全額払い」の原則を覆したのではなくて「①通貨払い」の原則を覆した事例だと思います。なぜなら現金で支払うところを一部ビットコインという通貨以外のもので本人に支払ったということであり、現金とビットコインのいずれも本人に支払われたということだからです。マネーの行き先が本人以外である「控除」ではないからです。
記事には「労使協定」で「①通貨払い」を覆すことができると書いてあるように見えますが「労使協定」で覆すことができるのは「③全額払い」です。「①通貨払い」を覆すことができるのは「労働協約」です。
これは間違いやすいポイントなので、社労士試験にも過去に何度も繰り返して出題されている有名なポイントです。
通訳前提(つうやくぜんてい)
このように語呂合わせをして、わたしは社労士試験に臨みました。
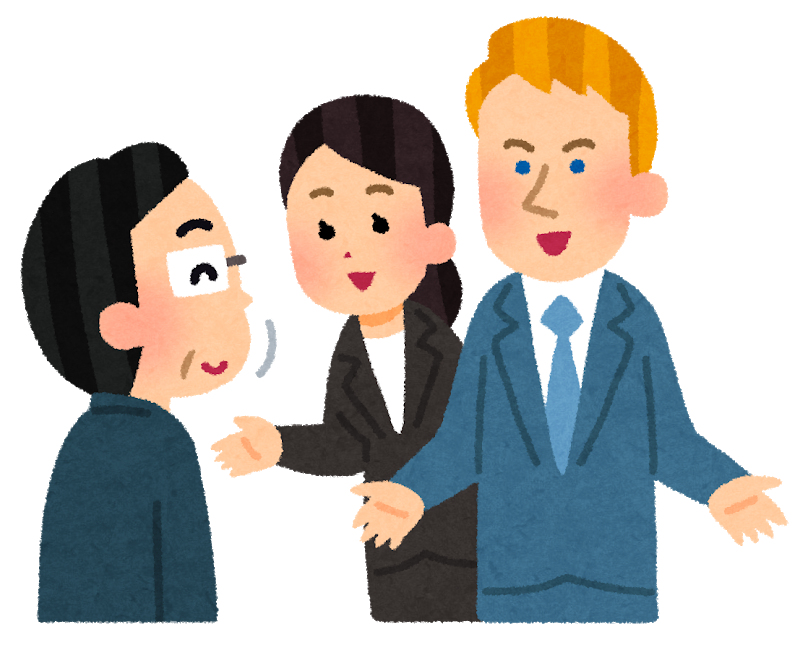
通約全定(つうやくぜんてい)
本当はこのような漢字をあてるのが正しいのだと思いますが、イメージとして「通訳前提」の方が個人的に呑み込みやすかったということです…
通貨払い=労働協約で覆る
全額払い=労使協定で覆る
こういう関係です。
記事にあるGMOインターネットグループが「労働協約」を結んで「①通貨払い」の原則を覆して、給与の一部をビットコインで支払ったということならば、GMOインターネットグループには労働組合が存在するのだと思います。なぜなら「労働協約」は「労働組合」と結ぶものだからです。裏を返せば「労働組合」がなければ「労働協約」を結ぶことができず、したがって「①通貨払い」の原則を覆すことはできないはずです。
「使用者と労働組合との間で労働協約を締結し、その現物の評価額を定めておかなければならない(労基則2②)」同ハンドブックP81
ビットコインの場合、時価が著しく変動することがあると思われ「現物の評価額」はどのように定めるのか、実務的には重要なポイントになると思います。
「LINEはスマホ決済で使える電子マネーを、社員向けに福利厚生の一環で毎月、給与とは別に配っている。」(同記事)
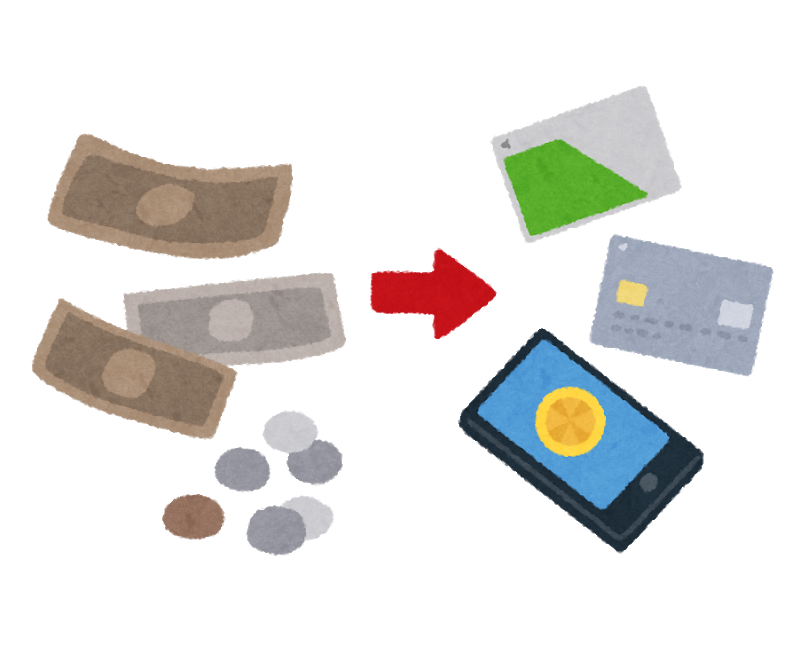
これは「給与と別」にすることにより「①通貨払い」の原則に抵触せずに運用できますので“軽やかに”支給できる技だと思います。
GMOの時は「支払」う、LINEの時は「配」ると書き分けているところは”わかってるなあ” ”さすがだなあ”と思いますので、労使協定のところが残念でなりません…
それはともかく!実務的には、現実の給与計算に取り組むとして、デジタル払いを前提にするとなると、所得税の源泉徴収額の決定や年末調整、労災支給時の金額決定の基礎となる「給付基礎日額」や失業した時に支給される基本手当額の基礎となる「賃金日額」や健康保険や厚生年金の保険料の額を決める「標準報酬月額」を計算するための基礎となる「賃金」にビットコインや電子マネーの”賃金性”をどのように特定して具体的にどのような額で参入するのかは、まだまだ研究の余地がありそうです。
社労士業務としてデジタルマネーはどうやら重要な分野に発展していきそうです。